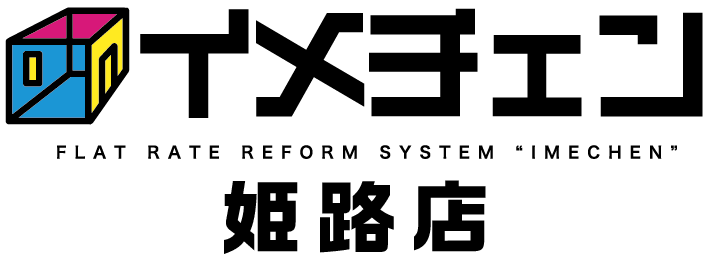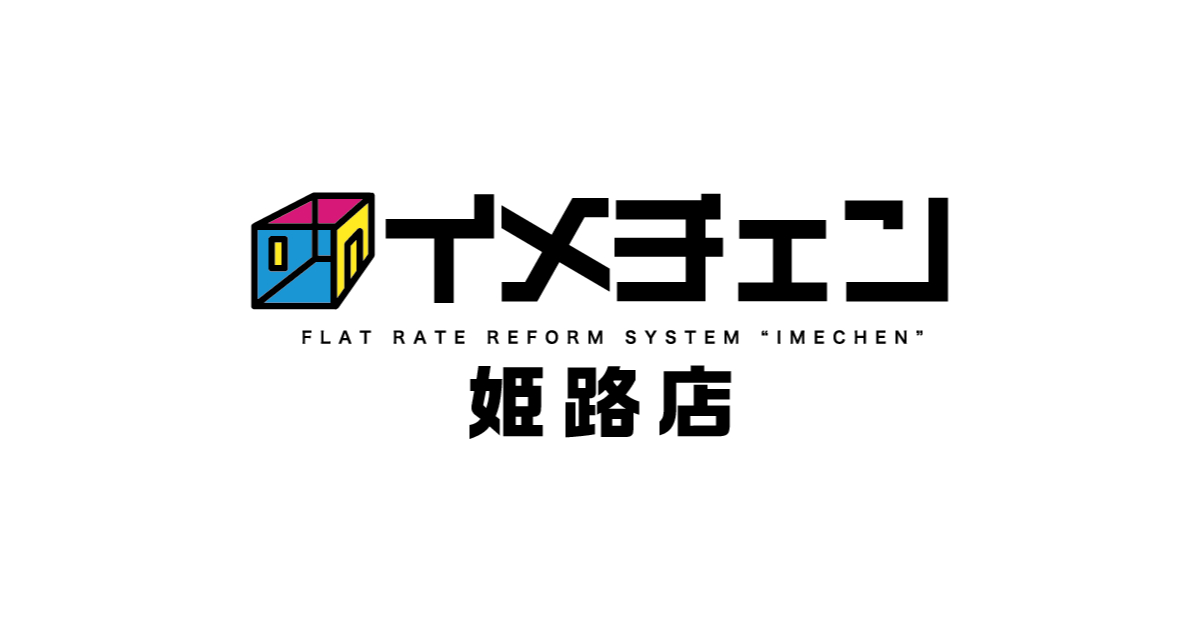- 浴室をリフォームする際、コスパの良いユニットバスの仕様はどんな仕様ですか?
-
必要な基本性能は押さえつつ、カウンターや棚などの設備を極力なくしたシンプルな仕様にし、必要なものはマグネット製品で後付けする方法です。これが初期費用と将来の掃除の手間を最も抑えられる、コストパフォーマンスに優れた仕様と言えます。
水回りのリフォームで、高額になりやすいのは、
- キッチン
- ユニットバス
この2点です。
高額なイメージのあるユニットバスリフォームですが、実はポイントを押さえるだけで、費用をぐっと抑えつつ、将来にわたって満足度の高い理想のバスルームを手に入れることが可能です。
今回は、単に価格が安いだけではない、掃除のしやすさや現実的な制約まで考慮した「本当の意味でコスパの良い仕様」を紹介いたします。
コスパの良い仕様は「何もない」ユニットバス+「後付け」アイテム
結論からお伝えすると、最もコストパフォーマンスに優れた仕様は、カウンターや固定棚、鏡などを極力なくした「ミニマルな仕様」です。
その理由は、初期費用が安いことに加え、掃除が圧倒的に楽になるからです。浴室の汚れで特に手ごわいカウンター裏のヌメリや鏡の水垢は、そもそも原因となる設備がなければ発生しません。日々のお手入れは、壁や床をサッと流すだけで完了。掃除の手間と時間、そして洗剤代も節約できるのです。
「でも、シャンプーを置く場所がないと困る…」という方もご安心ください。
最近のユニットバスはほとんど、壁のパネルが磁石が付くマグネット仕様になっているため、マグネット対応のアイテムを、必要になった時に必要なだけ後から自由に設置できます。
例えば、山崎実業のバスルームアイテムだと、バスラック、おもちゃフック、ディスペンサー、シャワーフック、風呂蓋スタンド、物干し竿ホルダー…など、マグネット対応のたくさんのアイテムがあります。






マグネットの良さは、掃除面だけでなく、後からでも位置を変えられることです。シャワーフックもマグネットだと、子どもの成長に合わせて高さを自由に変えられるので非常に便利になります。
マグネット系の収納はユニットバスメーカーでも販売していたりするのですが、後の追加も考えるなら全て後付けで対応した方が統一感は出やすいですね。また小物アイテムは、設備メーカーからすると専門ではないため、雑貨メーカーの方がコスト的にも優しかったりします。
マグネットのデメリットとしては、耐荷重面でしょう。例えば、マグネットの物干し竿ホルダーは、耐荷重6kgまでとなっています。ユニットバスのオプションで取り付けるネジで固定する場合だと、耐荷重は10kgまでとなっています。
このように、リフォーム時には最低限の「箱」だけを用意し、ライフスタイルに合わせてアイテムを足していく「引き算リフォーム」の発想が、コストを抑え、かつ将来的な満足度を高めやすくなります。
マグネットの耐久性は?
具体的な耐久年数は使用環境やお手入れの頻度によりますが、適切に扱えば数年以上にわたって問題なく使用できるケースがほとんどです。(◯年!と言い切っている情報がないので。。。)
マグネットの耐久性を考える上で、重要なポイントは「磁力」と「錆(サビ)」の2つです。
1. 磁力の低下について
まず磁石そのものの力(磁力)ですが、家庭のお風呂で普通に使用している限り、磁力が弱まって使えなくなるという心配はほとんどありません。
磁石の磁力は半永久的とも言われ、極端な高温にさらされたり、強い衝撃を与え続けたりしない限り、目に見えて低下することはありません。
2. 耐久性の最大の敵は「錆(サビ)」
マグネット製品の寿命を左右する最大の要因は「錆」です。特に湿気が多い浴室では、この錆対策が製品の品質を決めると言っても過言ではありません。
なぜ錆びるのか?
多くのマグネット製品は、スチール製の本体に塗装やメッキを施し、磁石部分をゴムや樹脂で覆う構造になっています。このコーティングが傷ついたり、経年劣化したりすると、そこから水分が侵入し、内部のスチールや磁石が錆びてしまうのです。発生した錆は、壁に茶色い「もらい錆」として付着してしまうこともあるため注意が必要です。
ただし、最近の製品は「錆びにくい」工夫がされている
この錆の問題に対応するため、現在市販されている浴室用のマグネット製品の多くは、以下のような工夫が凝らされています。
- ラバーコーティング: 磁石全体がゴムで覆われており、水分が直接磁石に触れにくくなっています。山崎実業のtowerシリーズなど、人気製品の多くがこのタイプを採用しています。
- 防錆(ぼうせい)加工: 本体がスチール製の場合でも、錆びにくいように何層もの塗装やコーティングが施されています。
- ステンレスや樹脂製の採用: そもそも錆びにくいステンレスや、錆びない樹脂(プラスチック)を本体の素材として使用している製品もあります。
ニトリの製品を1年間使用した方のレビューでは、特に錆や劣化は見られなかったという報告もあるようです。一方で、人気のある山崎実業towerシリーズでも、使い方によっては1年足らずで錆が発生したという声もあり、製品の品質だけでなく、使い方やお手入れも重要であることがわかります。
マグネット製品を長持ちさせる簡単なお手入れのコツ
高価なものではありませんが、せっかくなら長くきれいに使いたいですよね。以下の簡単なメンテナンスを心がけるだけで、耐久性は大きく向上します。
- 定位置にしない: 時々でいいので、設置場所を少しずらしたり、一度取り外したりして、本体と壁面に付いた水分を拭き取るのが最も効果的です。これにより、水垢やカビの発生も防げます。
- 優しく洗う: 掃除の際に、硬いタワシなどでゴシゴシこすると、表面の防錆コーティングが剥がれてしまう原因になります。柔らかいスポンジで優しく洗いましょう。
- 換気をする: 入浴後は換気扇を回すなどして、浴室全体の湿度を下げることも、錆の防止につながります。
【リフォーム特有の壁】サイズと窓の現実的な考え方
新築と違い、リフォームには既存の建物の構造という制約があります。特に「サイズ」と「窓」は、無理に変更しようとすると費用が大幅にアップする要注意ポイントです。
ユニットバスのサイズ選び:「既存と同じサイズ」になりやすい
リフォームの場合、現在設置されているユニットバスと同じサイズを選ぶことになりやすいです。
「元々のユニットバスのサイズより大きいサイズに…」と考えると、浴室周りの壁や柱の解体・移動といった大掛かりな工事が必要になり、費用が数十万円以上追加で発生していきます。なので、リノベーションするほどの工事内容でない限りは、大きくすることはないのです。
逆に小さくすることはコストを抑えられます。(例:元々1418サイズのユニットバスだったのに、1216にする等)ですが、コストのために、あえて小さくすることを求めますでしょうか?
窓の扱い:「既存の窓開口を活かす」が鉄則
元々お風呂に窓がある場合、その開口部を活かして新しいユニットバスを設置することになりやすいです。
窓そのものを「なくす」または「小さくする」場合、ユニットバスの工事とは別に、外壁の補修や塗装工事が追加で必要になり、大きなコストアップ要因となります。
「窓があると掃除が大変」という点は事実ですが、リフォームにおいては「窓をなくすコスト」の方が上回ることがほとんど。
特殊なケース:戸建てで在来工法の広い浴室だと、ワンサイズ小さいユニットバスで対応することも
古い戸建てでかつ広い家だと、ユニットバスではなく在来工法で、天井も高く広い浴室を作っていることがあります。

これを同じ様に在来でリフォームして仕上げたとしても、キレイにはなるが寒い浴室のままになってしまいます。なので、広い浴室なのであれば、その中で収まるようワンサイズ小さいユニットバスを設置することがあります。例えばこの場合だと、天窓もそのまま活かします。つまり、外から見たら天窓はそのままあるが、ユニットバス内は壁で窓の開口がない状態ということです。
「浴室乾燥機」の必要性を考える
ユニットバスのリフォームで、選択が分かれるのが「浴室乾燥機」の有無です。グレードにもよりますが、あるなしで10万円近い額が変わりますからね。
浴室乾燥機を洗濯物を乾かすために使用できるのは、浴室の広さからいっても一人~二人暮らしではないでしょうか?なので、洗濯物を干すためだけに設置しようとしているのなら、家族が増えれば増えるほど、必要ないのではないか?と思ってしまいます。
雨の日の洗濯物対策であれば、高性能な除湿機やサーキュレーターを部屋干しで活用する方が、コストも時間も効率が良いケースが多いです。また、戸建てなら「乾太くん」も有効的です。
ですが、中古住宅の場合、建物全体の断熱性能が今の新築住宅に比べると低いため、ユニットバスにしたとしてもまだ寒さを感じてしまうでしょう。なので浴室乾燥機を、ヒートショック対策や夏場ののぼせ防止、カビ予防のためにも使うのであれば、とても有用なものだと思います。
コスパの良いユニットバスのリフォームは、単に初期費用が安いことではありません。自分たちの暮らしに本当に必要なものだけを選び抜き、現実的な制約の中で無駄をそぎ落とすことで実現します。
- 仕様は「引き算」:カウンターや棚は付けず、マグネット製品で後からカスタマイズ。
- 制約は「活かす」:サイズや窓は既存のものに合わせ、追加工事を避ける。
- 業者は「比較する」:相見積もりで適正価格を知る。
この3つのポイントを押さえるだけで、費用を賢く抑え、満足度の高い「わが家だけの快適なバスルーム」が手に入ります。ぜひ、後悔のないリフォーム計画の参考にしてください。