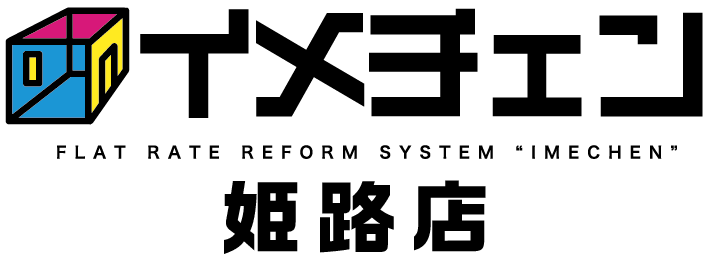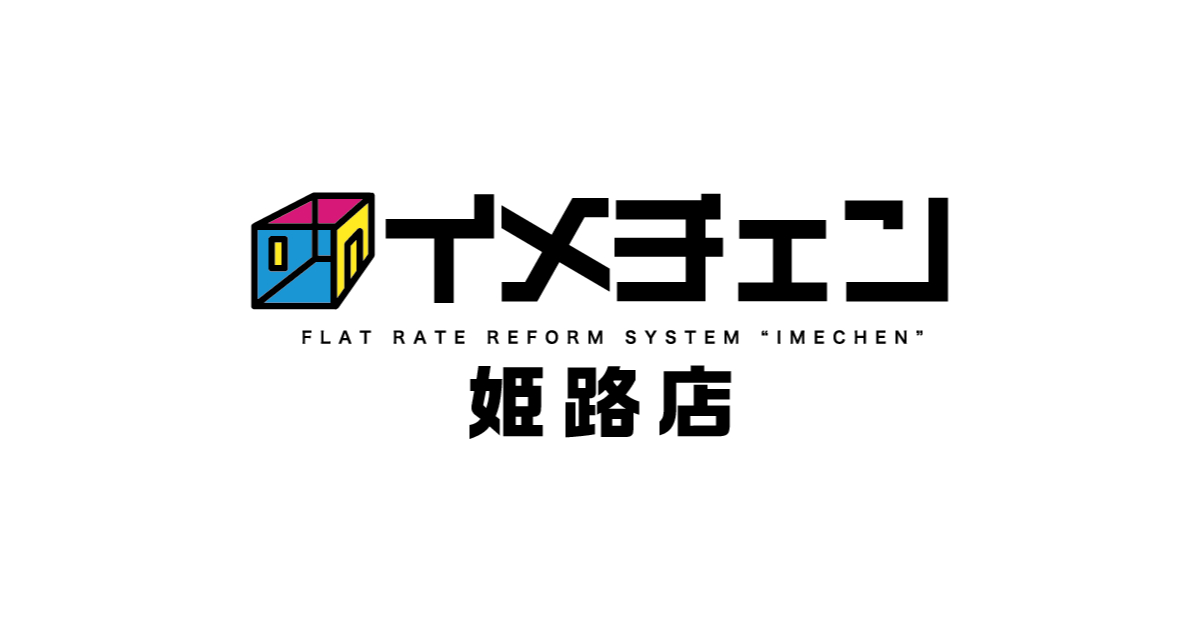- 価格の安い中古住宅の場合、リフォーム費用が高くなりませんか?
-
はい。価格が安い中古住宅の場合、リフォーム費用が高くなりやすい傾向があります。特に、古い中古住宅であればあるほど、基本性能が低い傾向になります。
姫路市で中古住宅を探していると、安い価格の物件に出会うことがあります。「この価格なら、浮いた予算で思い通りのリフォームができる!」と心が躍るかもしれません。しかし、その決断は少し待ってください。特に築年数が古い物件の「安さ」には、後から高額な費用となって跳ね返ってくる、見えないリスクが潜んでいる可能性があります。
この記事では、予算内で理想の住まいを手に入れるための知識として、物件選びの段階で知っておくべき「基本性能のリスク」と、見落としがちな「古い内装仕様のリスク」を解説いたします。
【基本性能編】「物件価格の安さ」に潜む3大リスク
まず考えるべきは、建物の骨格となる基本性能です。ここを見誤ると、リフォーム費用は一気に跳ね上がります。
1. 構造体の劣化
「構造体」とは、柱、梁、土台、基礎など、建物を支える骨格部分のことです。ここが劣化していると、建物の安全性そのものが脅かされ、修繕には莫大な費用がかかります。
- 雨漏りが引き起こす木材の腐食
屋根や外壁のひび割れから侵入した雨水は、気づかぬうちに壁の内部や柱を濡らし、木材を腐らせてしまいます。見た目は問題なさそうでも、壁を剥がしてみたら柱がボロボロだった…というケースは少なくありません。 - シロアリ被害の恐怖
湿気を好むシロアリは、床下や壁内部の木材を食い荒らします。被害が進行すると、土台や柱がスカスカになり、家の強度を著しく低下させます。地震などの際に倒壊する危険性も高まります。
これらの修繕は、壁や床を一度すべて剥がして骨組みの状態にし、腐食したり被害に遭ったりした木材を交換・補強するという大掛かりな工事になります。被害の範囲によっては、シロアリの駆除費用に加えて数百万円単位の補修費用がかかることもあり、まさに「安物買いの銭失い」の典型例となってしまうのです。
2. 耐震性の不足
日本は地震大国であり、姫路市も将来発生が懸念される南海トラフ巨大地震では、震度6強の揺れや津波の被害が想定されています。そのため、住まいの耐震性は命を守る上で最も重要な要素の一つです。
高額になりがちな耐震補強工事
耐震補強は、基礎をコンクリートで補強したり、壁の内部に筋交いや構造用合板を入れて壁を強くしたり、柱と土台が抜けないように金物で固定したりする工事です。建物の状態や補強範囲によりますが、一般的に150万円前後の費用がかかり、大規模な場合は200万円を超えることも珍しくありません。
「旧耐震基準」と「新耐震基準」の決定的違い
日本の建築基準法における耐震基準は、1981年6月1日を境に大きく変わりました。
- 旧耐震基準(~1981年5月31日)
震度5強程度の揺れで「倒壊しない」ことが基準。 - 新耐震基準(1981年6月1日~)
震度5強程度では「ほとんど損傷せず」、震度6強~7の揺れでも「倒壊・崩壊しない」ことが基準。
過去の阪神・淡路大震災では、旧耐震基準の建物に被害が集中したことが報告されており、その差は明らかです。旧耐震基準の物件を現在の基準まで引き上げるには、耐震補強工事が必須となります。
3. 断熱性の低さ
「昔の家は夏暑くて冬寒い」とよく言われますが、その主な原因は断熱性能の低さにあります。特に1999年以前の住宅は、現在の省エネ基準をはるかに下回ることが多く、壁の中に断熱材が入っていない「無断熱」の家も少なくありません。
無断熱がもたらすデメリット
- 高い光熱費
断熱性が低いと冷暖房の熱がすぐに外へ逃げてしまうため、エアコンが効きにくく、光熱費が余計にかかります。 - 健康へのリスク
部屋ごとの温度差が激しくなり、冬場には暖かいリビングから寒い脱衣所やトイレへ移動した際に血圧が急変動する「ヒートショック」のリスクが高まります。 - 結露とカビの発生
外気との温度差で窓や壁に結露が発生しやすく、カビやダニの温床となり、アレルギーなどの健康被害を引き起こす可能性もあります。
快適で健康的な暮らしを送るためには、壁・床・天井への断熱材の充填や、熱が出入りしやすい窓を断熱性の高いものに交換するといった断熱リフォームが非常に効果的です。しかし、これも家全体となると高額な費用がかかります。
どこまでの基本性能を求めるか?そのバランスが大事
では、最高の性能にリフォームしたら?どうなるのでしょうか?
YKK APが「性能向上リノベーション実証プロジェクト」として、複数の実物件で最高レベルの断熱・耐震改修を行っており、その費用が2000万円を超えるとのこと。下手をすると新築より高くなってしまう可能性もあります。
逆に、旧耐震安い中古住宅を求める方の場合、耐震性や断熱性に関しては性能の低さを承知で、初期費用の安さを優先している方が多いことは否めません。(正直、建築的な視点ではオススメはできないです…)
- 得られる効果(メリット)
- 購入価格の安さ:初期投資を大幅に抑えることができます。
- 犠牲になるもの(デメリット)
- 耐震性の低さ: 地震発生時の安全性が低く、命や財産を守る上でのリスクが高まります。
- 断熱性の低さ: 夏は暑く冬は寒いため、快適性が損なわれます。また、冷暖房の効率が悪く、光熱費が高くなる傾向があります。
- 将来的なコスト: 耐震補強や断熱リフォームを行う場合、追加で大きな費用が発生する可能性があります。
つまり、「初期費用の安さ」というメリットを得るために、「安全性」「快適性」「将来の光熱費やリフォーム費用」といった要素を犠牲にしているというトレードオフの関係にあるということでもあります。
日本の住宅は、建築基準法の改正の歴史とともに、その仕様、特に耐震性、断熱性、そして室内環境に関する基準が段階的に強化されてきました。
なので、中古住宅の取得もリフォーム費用も、コスパ良く選択していくなら、年代別の住宅の傾向をある程度知っておいた方がいいですね。自身のライフスタイルと照らし合わせ、どこまでの基本性能を求めるのか?そのバランスも意識しておきましょう。
もちろん、その求める中古住宅が現れるかどうかはまた別の問題で難しいところですが・・・
失敗しないための羅針盤!購入前の「住宅診断」は必須
ここまで見てきたように、古い中古住宅には目に見えない多くのリスクが潜んでいます。これらのリスクを事前に把握せずして、安心して購入することはできません。
そこで強く推奨したいのが、購入契約前に専門家による「ホームインスペクション(住宅診断)」を実施することです。(特に戸建て住宅。)これは、建築士などの専門家が第三者の立場で、建物の劣化状況や欠陥の有無、改修すべき箇所を診断してくれる「家の健康診断」のようなものです。
例えば、弊社で提供している「建物検査+シロアリ検査」では、以下のようなことを行います。
| 建物検査 | 手の届く範囲での触診検査ならびに観察できる範囲での目視検査および一部計測器による検査を実施します。 ①屋外(外壁・軒裏・開口部(ドア・サッシ)・バルコニー・屋根・土台・床組) ②屋内(柱・内壁・天井・小屋組・床・基礎) ③給排水管路(屋外・床下・天井裏・キッチン・浴室・洗面所・トイレ・外壁貫通部) |
| シロアリ検査 | ・床下環境(カビの有無・腐朽、シロアリの蟻道、被害の有無) および建物外周、玄関まわり等のシロアリの害について検査を実施します。 |
これにより、
- 屋根や外壁の劣化、雨漏りの痕跡
- 床下のシロアリ被害や構造材の腐食の有無
- 建物の傾き
- 今後修繕が必要となる箇所と、その時期や費用の目安
などがわかり、通常では見えなかったコストが見えてくるようになります。
【内装編】見た目以上に厄介!古い仕様が高くつく理由
建物の基本性能に問題がなくても、次に待ち構えるのが「内装」の壁です。一見簡単なリフォームで済みそうに見えても、古い住宅特有の仕様が「追加工事」を発生させ、費用を押し上げます。
和室を洋室にする際の問題
現代の住宅の壁や天井は、石膏ボードという平滑な板の上にクロス(壁紙)を貼る「大壁(おおかべ)」仕様が主流です。しかし、古い住宅に多い和室では全く異なる工法が用いられています。
和室をそのまま和室として使うならコストは抑えられますが、その和室を洋室化したい場合、それなりのコストが掛かってしまいます。


- 壁:真壁(しんかべ)から大壁への変更コスト
和室でよく見られる、柱が見える「真壁」を、柱が見えないスッキリとした「大壁」に変えるには、単純にクロスを貼ることはできません。柱の間に下地となる木材を組み、その上に石膏ボードを張って初めてクロスが貼れる状態になります。この下地造作の手間と材料費が、想像以上にかかるのです。 - 壁:砂壁・土壁・繊維壁の下地処理コスト
昔ながらの砂壁や土壁は、それ自体がポロポロと剥がれ落ちやすいため、直接クロスを貼ることはできません。クロスを貼るためには、表面を固める処理をしたり、薄いベニヤ板を上から全面的に張ったりといった「下地処理」が必須となります。このひと手間が、工期と費用を増加させます。 - 天井:竿縁天井(さおぶちてんじょう)の存在
和室によくある、細い木材(竿縁)が渡された「竿縁天井」も厄介です。これを現代風のフラットな天井にするには、既存の天井を解体したり、竿縁の間に下地を組んでボードを張ったりする必要があり、手間と費用がかかります。 - 床:畳からフローリングへの変更に伴う下地調整
和室の畳を剥がして、そのままフローリングを敷けば良いと考えがちですが、それではうまくいきません。畳には5~6cmほどの厚みがありますが、一般的なフローリング材の厚さは1.2cm程度です。そのため、畳を撤去しただけでは床が大きく下がり、隣室との間に大きな段差が生まれてしまいます。この段差を解消するために、床の高さを調整する作業が必須となります。
【年代別】コスパで見る狙い目な築年数と特徴
中古住宅の取得とリフォーム費用をコストパフォーマンス(コスパ)良く選択していく上で、最も重要な指標は「耐震基準」になります。
最もコスパが良い狙い目:築25年〜40年程度(1981年〜2000年頃)
この年代の住宅は「新耐震基準」を満たしているため、建物の基本的な安全性に一定の信頼がおけます。
- メリット:
- 価格が手頃
新築や築浅物件に比べて価格が大きく下落しており、取得費用を抑えられます。 - 安全性の基礎
新耐震基準を満たしているため、旧耐震物件のような大規模な耐震補強が不要な場合が多いです。 - 選択肢の豊富さ
流通量が比較的多く、希望の立地で見つけやすいメリットもあります。
- 価格が手頃
- 注意点:
- 断熱性能
現在の基準と比べると断熱性能が低い場合があります。リフォームで断熱材を追加するなどの対策を検討すると、快適性と光熱費の削減につながります。 - 設備の劣化
キッチン、浴室、給湯器などの住宅設備は寿命が15年〜25年程度のため、購入後に交換が必要になる可能性が高いです。リフォーム費用としてあらかじめ見込んでおきましょう。 - メンテナンス履歴
これまでの修繕履歴を確認し、建物の状態を把握することが重要です。
- 断熱性能
価格と性能のバランスが良い:築20年〜25年程度(2000年以降)
2000年基準を満たした、より高い耐震性が期待できる年代です。
- メリット:
- 高い耐震性
2000年基準により、耐震性の信頼度がさらに高まります。 - 比較的新しい設備
築20年前後であれば、まだ使用できる設備が残っている可能性があり、リフォーム費用を抑えられる場合があります。
- 高い耐震性
- 注意点:
- 価格: 築年数が浅い分、価格は高めになる傾向があります。
注意が必要(上級者向け):築40年以上(1981年以前の旧耐震)
物件価格の安さは非常に魅力的ですが、多くのリスクと追加費用を伴います。
- メリット:
- 圧倒的な価格の安さ
建物価格がほぼゼロに近く、土地代のみで手に入れられるケースもあります。
- 圧倒的な価格の安さ
- デメリット:
- 高額な耐震補強費用
安全に住むためには、耐震補強工事が必須となる可能性が高く、数百万円単位の費用がかかります。 - 住宅ローン・税制面の不利
住宅ローンの審査が厳しく、原則として住宅ローン控除も利用できません。地震保険料も割高になります。 - 大規模なリフォーム
断熱材が入っていなかったり、配管や配線が寿命を迎えているなど、構造部分から見直す大規模なリフォームが必要になることが多いです。
- 高額な耐震補強費用
結論:コストパフォーマンスを最大化するためのポイント
- 「1981年6月以降」を条件にする
まずは新耐震基準を満たしている物件に絞って探しましょう。 - 築20年〜40年(1981年〜2000年頃)をメインターゲットに
価格と基本的な安全性のバランスが最も良いこの年代を中心に物件を探し、リフォーム費用を含めた総額で比較検討するのが賢い選択です。 - 物件の状態を必ず確認する
同じ築年数でも、メンテナンス状況によって建物の状態は大きく異なります。購入前には、専門家によるホームインスペクション(住宅診断)を利用して、目に見えない劣化や欠陥がないかを確認することを強くお勧めします。
最終的には、物件の価格だけでなく、リフォーム費用、そして将来のメンテナンスコストまで含めた「トータルコスト」で判断することです。表面的な物件価格に惑わされず、購入前の住宅診断で建物の真の状態を把握し、古い内装のリフォームに潜む「隠れたコスト」まで理解することが、予算オーバーを防ぎ、後悔しない中古住宅選びの鍵となります。