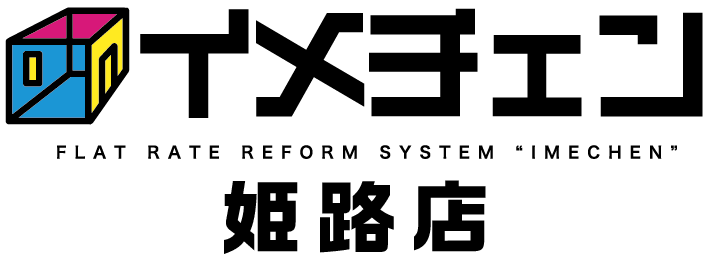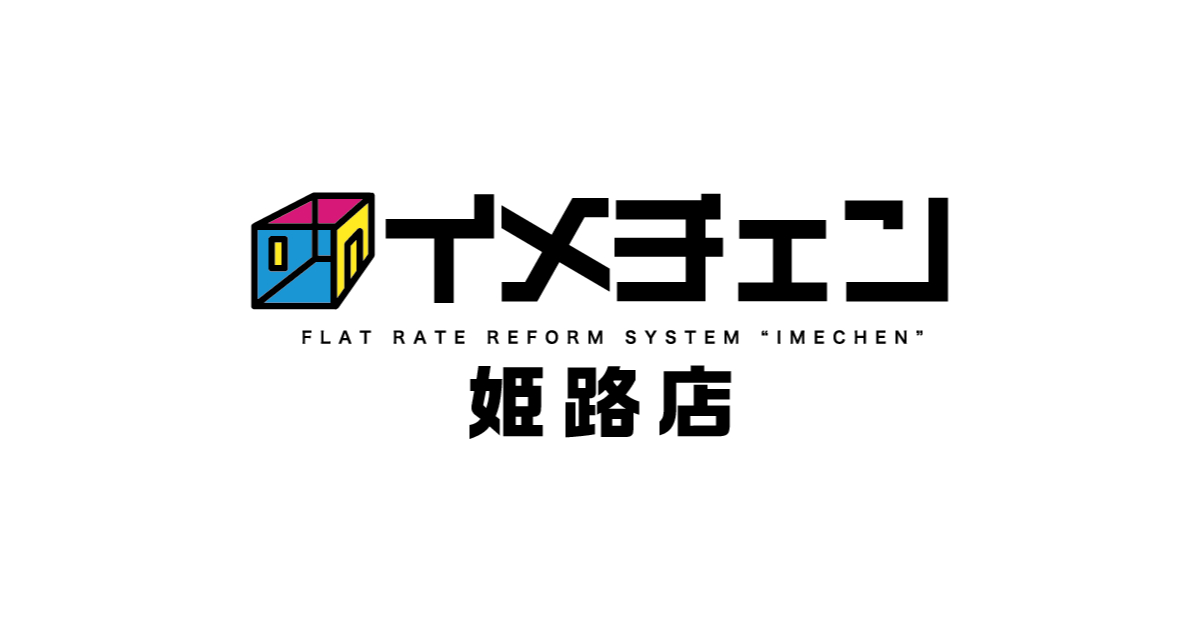- 中古住宅を購入後に「一部分のリフォーム」と「フルリフォーム」どちらが良いでしょうか?
-
「一部分のリフォーム」は後で後悔しやすいため、「フルリフォーム」をオススメします。
弊社でも昔は施主の要望を優先して一部分リフォームを請けていたのですが、完成した出来上がりを見て、工事をした新しい箇所と工事をしなかった古い箇所の差が目立ち、「全部すればよかった」と追加工事になるケースばかりでした。
そのため今では最初の提案の際、施主が一部分リフォームを考えられていても、予算が大丈夫なのであればフルリフォームを提案をしております。
後悔しやすい!中古住宅購入後の「一部分リフォーム」という罠
そもそも、なぜ多くの人が一部分リフォームを選んでしまうのでしょうか。そこには、私たちの誰もが陥りがちな心理的な「罠」が潜んでいます。
罠①:「予算の壁」という思い込み
中古住宅の購入は、人生で最も大きな買い物の一つ。物件価格の支払いで頭がいっぱいになり、「リフォームは、まあ余ったお金で…」と考えてしまうのは自然なことです。しかし、ここに最初の罠があります。
本当に考えるべきは「物件価格+リフォーム費用=マイホームの総額」です。この総額で資金計画を立て、必要であれば「リフォーム一体型ローン」などを活用するのが現代の賢い家の買い方。この選択肢を知らないまま「手元にあるお金の範囲で」と考えてしまうと、必然的に「一部分だけ」という中途半端な選択しかできなくなってしまうのです。
罠②:「手軽さ」という甘い誘惑
「住みながら工事できる」「2週間で終わる」といったリフォーム会社の謳い文句は、とても魅力的に聞こえます。新しい生活を早くスタートさせたいという気持ちも相まって、「とりあえず手軽にできる範囲で」と決断してしまいがちです。
しかし、その手軽さの裏には、「空間全体のデザインが破綻する」という最大のリスクが隠されています。そのリスクを見過ごしたまま契約書に印鑑を押してしまった瞬間から、後悔へのカウントダウンが始まっているのかもしれません。
罠③:「この部分はまだキレイ」という幻想の罠
これこそが、一部分リフォームで最も多くの人が心を折られてしまう、最も恐ろしい罠です。
中古住宅の内見時、あなたはこう考えたはずです。「キッチンはさすがに古いけど、リビングのフローリングはこのエリアはまだ十分キレイだ。壁紙もこの一面だけ張り替えれば問題ないだろう」と。そして、汚い部分だけをリフォームする計画を立てます。
工事が完了し、ピカピカのキッチン、真っ白な壁紙や新しい床が目の前に現れます。その瞬間は感動するでしょう。しかし、その感動が冷めやらぬうちに、あなたの視線は、残す判断をした「まだキレイなはず」の箇所へと移ります。
すると、どうでしょう。昨日まで何とも思わなかったフローリングや壁紙の小さな傷、日焼けによる微妙な色褪せ、隅に溜まった取り切れない汚れが、まるで拡大鏡で見たかのように、はっきりと、無慈悲に目に飛び込んでくるのです。
新しい部分の「100点の輝き」が、これまで「70点で合格」だと思っていた既存部分を、容赦なく「30点の落第」に引きずり下ろす。 これが、この罠の正体です。きれいだと思っていた部分が、新しい部分との残酷な比較によって、急にみすぼらしく、汚れた存在へと成り下がる。この裏切られたような感覚こそが、「こんなはずじゃなかった」という強烈な後悔を生むのです。
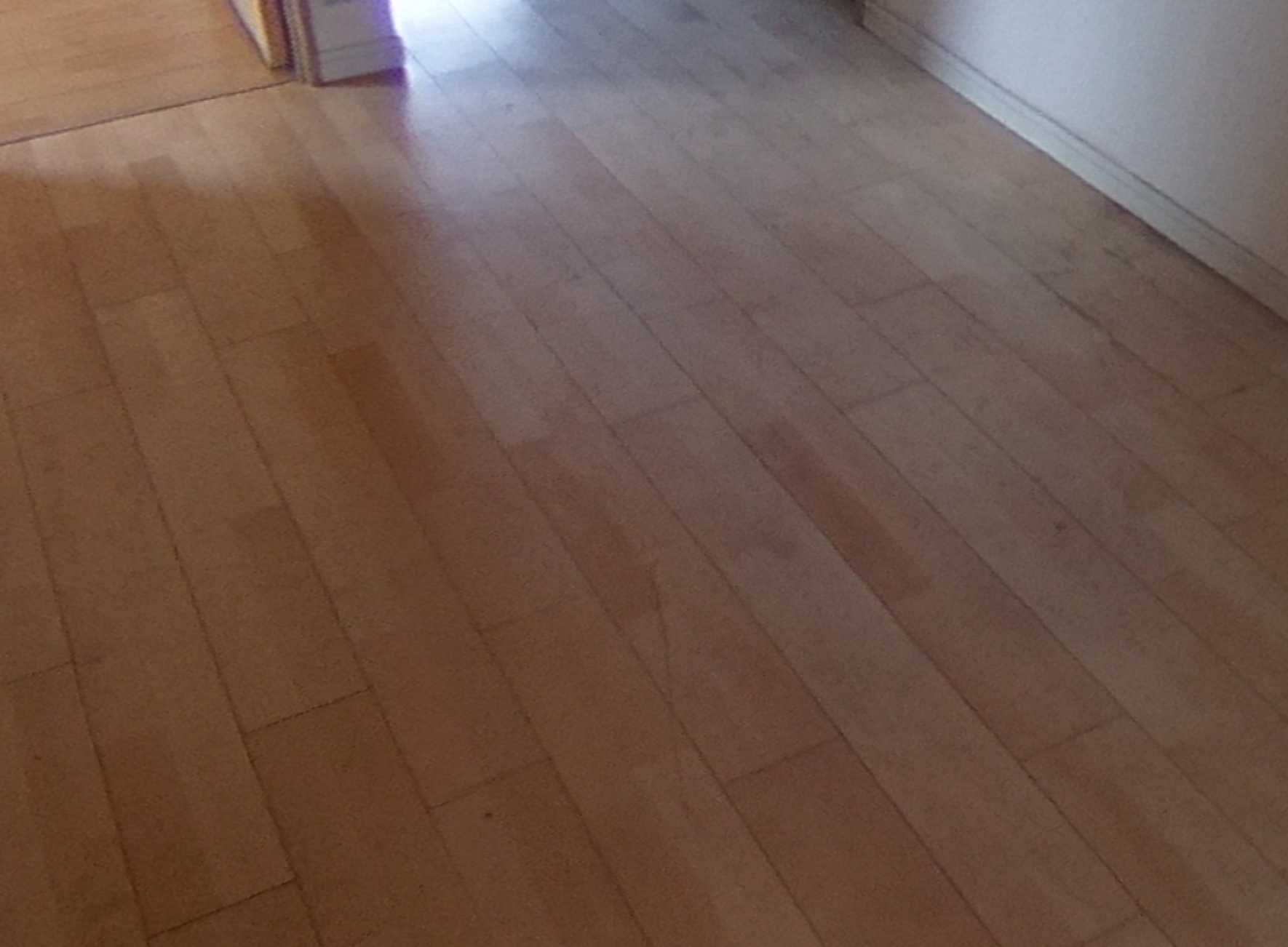
要注意!部分リフォームで後悔を招きやすいスポット
部分リフォームの失敗は、新しくした「そのもの」で起きるわけではありません。その「新しい部分」の周囲で発生します。
問題の核心は、新しい部分の「新しさ」が、これまで許容できていた既存部分の古さや汚れを、無慈悲に照らし出してしまう現象にあります。具体的に、家の中のどこでその悲劇が起きやすいのか、エリア別に見ていきましょう。
空間の額縁となる「境界線」
壁や床といった大きな面を新しくしたとき、その「境界線」で違和感が生まれます。
- 床の境目: LDKの床だけを張り替えた結果、隣の部屋や廊下との接続部分で色や質感がくっきりと断絶。家全体が「つぎはぎ」のパッチワークのような印象に。
- 壁と天井の境目: 真っ白になった壁紙が、見上げて初めて気づく天井全体の黄ばみや黒ずみを際立たせます。
- 壁と床の境目(巾木): 新しい壁と床に挟まれた、傷だらけで黄ばんだ巾木。それは、美しい絵画を汚れた額縁に入れているようなもので、空間全体が安っぽく見えてしまいます。
空間の印象を支配する「建具」
壁がきれいになると、今まで風景に溶け込んでいたドアや窓枠が、急に主役として浮かび上がってきます。
- 室内ドア・クローゼット扉: 真っ白な壁というキャンバスに、一昔前のデザイン(例えば、赤みの強い木目調)のドアが、時代遅れの絵画のように飾られている状態に。古いデザインのドアノブに触れるたび、現実に引き戻されます。
- 窓枠・ドア枠: 新しい壁紙に縁取られることで、これまで気にならなかった枠の黄ばみや結露によるシミ、表面シートの剥がれが、まるでアート作品のように目立ってしまいます。
壁面に点在する「生活のスイッチ類」
壁という美しいステージの上に残された、時代遅れの小道具たち。毎日目にし、手で触れるからこそ、小さな違和感がストレスとして蓄積されます。
- スイッチ・コンセントプレート: 真っ白な壁にポツンと残された「黄ばんだシミ」にしか見えなくなります。
- 給湯器・インターホンモニター: 壁に埋め込まれた「古い家電」のデザインが、空間のモダンな雰囲気を一瞬で破壊します。
- 分電盤・エアコン: どうしても生活感を隠せない「巨大な異物」として、新しい壁の上で悪目立ちします。
見落としがちな「仕上げの小物」
主要な工事が終わり安心した頃に気づく、細部のがっかりポイントです。
- 照明器具: 空間の真ん中で、古臭いデザインの照明が部屋全体の印象を決定づけてしまいます。
- カーテンレール: 壁や窓がきれいになっても、窓辺の印象を決めるレールが日焼けして変色していると、全てが台無しに感じられます。
以上、これらの箇所はすべて、リフォームした部分に「隣接」しているために問題となります。単体で見て「まだ使える」と判断したものが、新しいものとの「比較による落差」によって「気になってしまうほど古いもの」に見えてしまう。これこそが、部分リフォームでは満足度が上がらない最大の原因なのです。
「新旧」が絶対に調和しない科学的・デザイン的根拠
これらの失敗は、単に「センスがなかった」という問題ではありません。新しいものと古いものが、本質的に調和できない、科学的・デザイン的な根拠があるのです。
根拠①:避けられない「経年変化」という物理法則
新品の工業製品が持つ均一な美しさと、10年、20年という時間の中で紫外線や人の手に触れ、無数の傷や色の変化を刻んできた既存部分。両者の間には、ごまかしようのない「時間の溝」が存在します。これは物理法則であり、どんなリフォーム技術をもってしても完全に埋めることは不可能です。新しい部分が完璧であればあるほど、古い部分が持つ時間の痕跡は、かえって悪目立ちしてしまうのです。
根拠②:デザインにおける「トレンドの賞味期限」
ファッションに流行があるように、住宅の建材や設備のデザインにもトレンドがあります。10年前に主流だった少し赤みのある光沢仕上げのフローリングと、現代のトレンドであるマットでグレイッシュな建具。これらを同じ空間に同居させるのは、80年代の肩パッドジャケットに最新のスキニーパンツを合わせるようなもの。高度なデザイン計算なしに行えば、単なる「時代遅れと現代のちぐひぐな組み合わせ」にしかなりません。

根拠③:人間の脳を騙す「対比効果」という心理現象
これは、あなたの感覚が狂ったわけではありません。人間の脳は、隣り合うものを比較して認識する性質があります。これを心理学で「対比効果」と呼びます。真っ白な壁紙の隣にあるスイッチプレートは、実際以上に黄ばんで見え、ピカピカの床の隣にあるドアは、実際以上に古びて見える。これは人間の脳の仕組み上、避けられない現象であり、一部分リフォームが必ず違和感を生む根本的な原因なのです。
後悔しないための、たった2つの確実な道
では、どうすればいいのか。答えはシンプルです。中途半端な選択をせず、覚悟を決めて、以下のどちらかの道を選ぶことです。
選択1:【理想を叶える王道】フルリフォーム
後悔を避けるための最も確実で、最終的に満足度が最も高くなる選択肢です。
- 完璧な統一感: 床、壁、天井、建具、設備を全て一新するため、「新旧のちぐはぐ感」は絶対に生まれません。あなたの理想を、ゼロから真っ白なキャンバスに描くことができます。
- 根本的な問題解決: 見た目だけでなく、断熱材の追加による省エネ化、耐震補強による安全性向上、給排水管の刷新による漏水リスクの回避など、建物の性能を根本からアップデートできます。この「見えない価値」こそが、日々の暮らしの質と安心を支えます。
- 資金計画の具体策: 前述の通り、「リフォーム一体型ローン」を活用すれば、物件購入とリフォームの支払いを一本化できます。月々の返済額として捉えることで、資金計画も立てやすくなります。まずは金融機関や信頼できるリフォーム会社に相談してみましょう。
弊社もできる限り、壁床天井のフルリフォームができるよう、予算配分を考えて提案をしております。「表層リフォーム+水回りの交換(キッチン・ユニットバス・洗面・トイレ)」だと400万円ぐらいが一つの目安になります。水回りがきれいな状態であればそのまま使用したりしますが、壁床天井の表層リフォームはフルリフォームをオススメしております。
選択2:計画に基づいた「段階的リフォーム」(ただし、強い意志と計画性が求められる)
どうしても一度に全ての費用を捻出するのが難しい場合は、この選択肢があります。ただし、これは「とりあえず」の一部分リフォームとは全くの別物とお考えください。
- まず、家全体の「リフォーム計画」を作る
- 工事をフェーズ分けする
- 計画通りに実行する
最初に信頼できるリフォーム会社に相談し、将来の理想の住まいの「計画」を一緒に作り上げます。その計画に基づき、「入居前は表層リフォーム」「3年目はユニットバス交換」というように、優先順位をつけて工事計画を立てます。そしてそれを実行します。
例外:一部分リフォームが許容されるごく稀なケース
ここまで一部分リフォームのリスクを強調してきましたが、ごく稀に許容されるケースも存在します。
- ケース①:築浅物件で「純正パーツ」が手に入る場合: 築年数が浅く、メーカーから全く同じ型番の建具や床材が手に入る場合。
- ケース②:視線が完全に遮断された独立空間の場合: 例えば、普段は使わない2階の個室の壁紙を張り替えるなど、他の空間との連続性が全くない場合。
- ケース③:プロが意図的に行う「デザインとしての不協和音」の場合: 高度なデザイン知識を持つプロが、あえて新旧の対比をデザインとして成立させる場合。
ただし、これらは極めて限定的な状況であり、ほとんどの方には当てはまらないと考えてよいでしょう。
リフォームを「修繕」ではなく「未来の暮らし」への投資と捉える
中古住宅を購入して入居前にするリフォームの場合、リフォームに対する考え方を少しだけ変えてみることをお勧めします。それは、リフォームを単なる「修繕」と捉えるのではなく、「これからの暮らしやすさへの準備」と考えることです。
- 「修繕」とは、目の前の汚れや古さが気になる箇所を直し、最低限住める状態にすることです。これは短期的な視点と言えます。
- 「準備」とは、これから始まる新しい生活が、より快適で満足できるものになるように、空間全体を整えることです。こちらは長期的な視点です。
一部分リフォームという「修繕」の発想では、入居した後に「やっぱり、あそこも直しておけばよかった」という気持ちが生まれやすくなります。新しい生活が始まってから追加で工事をするのは、住みながらになるため手間もストレスもかかります。
一方で、入居前のフルリフォームは、「暮らしやすさへの準備」として非常に合理的です。
家具や荷物がない状態での工事は、効率が良く、費用や工期を抑えることにも繋がります。そして何より、入居したその日から、統一感のあるすっきりとした空間で新生活をスタートできます。
フルリフォームは、確かに初期費用がかかります。しかしそれは、入居後に感じるであろう小さな不満や追加工事の手間を先回りして解消し、これから長く続く「気持ちのいい毎日」を手に入れるための準備と考えることができます。
だからこそ私たちは、入居前のこの貴重な機会に、目先のコストだけでなく、これから何十年と続く暮らしの快適さという視点を持って、リフォーム計画を立てることをお勧めしています。