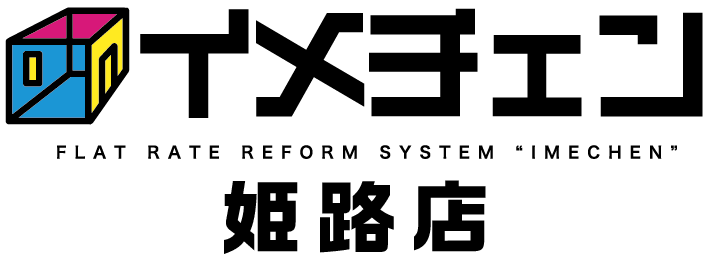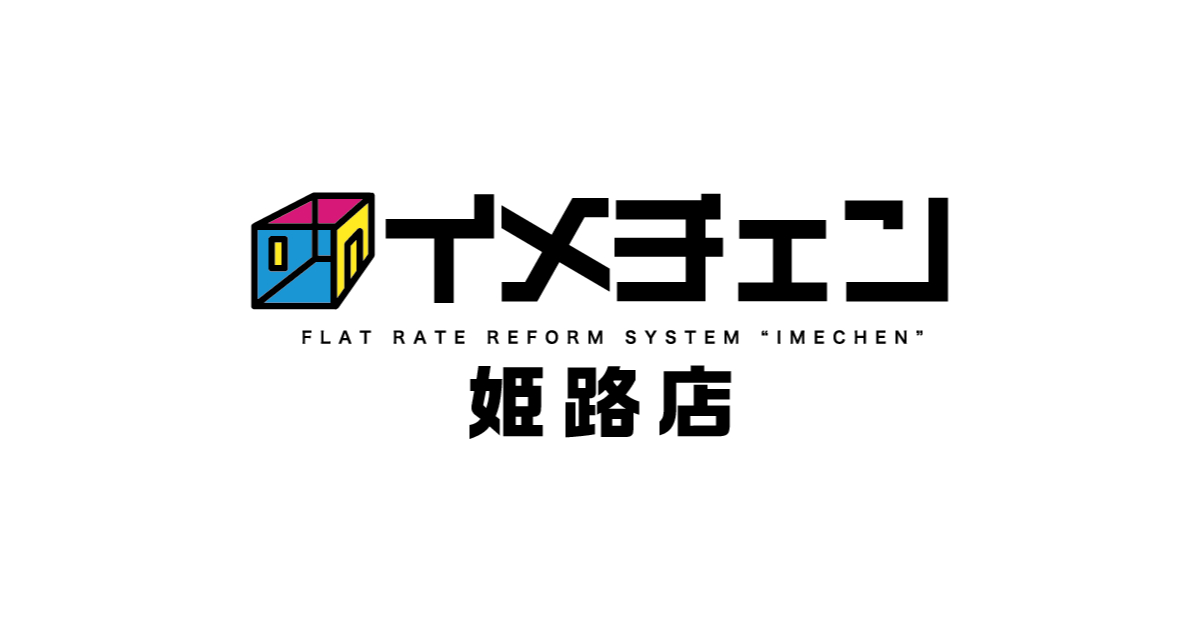- 「給湯器」は中古住宅購入時に交換した方が良いですか?
-
はい。特に製造から10年以上経過している給湯器は、入居後の突然の故障による高額出費や生活の不便を避けるため、購入時のリフォームに合わせて交換するのが賢明です。
以前、中古住宅の購入検討時に、元の設備機器の動作確認をおこなうことを推奨しました。
そういった設備機器の中に一つで、よく見落としなのが、「給湯器」です。
キッチン、ユニットバス、洗面、トイレなどの宅内の主要な設備とは異なり、「給湯器」は外に設置されていることが多いため、確認することを忘れるケースが非常に多いです。
中古住宅の給湯器をそのまま使用し、入居後すぐに給湯器が故障し、「想定外の数十万円の出費」「真冬に数日お湯が使えない」といったトラブルは、中古住宅購入のあるあるな失敗談です。
キッチンやユニットバスに隠れて、注目されるような設備ではありませんが、給湯器はインフラ設備なので、生活の満足度を左右する重要な土台となっているのです。
古い給湯器がもたらす3つの深刻なリスク
リスク1:生活設計を破壊する「資金計画の爆弾」
入居直後の故障は、生活に不便をもたらすだけではありません。給湯器の交換には、本体価格と工事費を合わせて15万円~35万円ほどの費用がかかります。追い焚き機能や乾燥機能、ミスト機能など多機能になればなるほど、さらに高くなります。
これは、新生活の家具や家電の購入、引っ越し費用などで物入りな時期において、極めて大きな「計画外の出費」となってしまいます。
リスク2:QOL(生活の質)を著しく下げる「ライフラインの麻痺」
「お湯が出ない」という事態は、想像以上に大変です。
- 衛生面の問題
小さなお子様がいるご家庭では、お風呂や衛生管理が困難になり、死活問題に発展しかねません。 - 時間的・金銭的コスト
お湯が使えなくなり一時的にしのぐ方法としては、銭湯に通うなどが考えられます。ただし、時間もお金もかかります。近所に銭湯がなければ、その負担はさらに増大します。 - 精神的ストレス
「シャワー中に突然水になる」「いつ壊れるか分からない」という不安は、日々の生活に大きなストレスを与え続けます。
リスク3:後からでは手遅れな「機会損失」
「壊れた時に交換すればいい」という考え方も、実は損をしています。リフォーム完了後に給湯器を交換する場合と、引っ越し前のリフォームと同時に行う場合に比べて、以下のような機会を失うことになります。
- コスト削減の機会
本来一度で済んだはずの工事を分割することで、割高な工事費を支払うことになります。 - ローン活用の機会
住宅ローンに組み込むチャンスを逃し、現金での一括支払いか、金利の高い別のローンを組む必要が出てきます。 - 補助金活用の機会
省エネ設備に対する補助金は、予算や期間が限定されています。タイミングを逃すと、利用できなくなる可能性があります。
不動産会社はあてにならない?給湯器チェックリスト
「内覧の時、不動産会社の担当者は『特に問題ないですよ』と言っていたのに…」というのは、中古住宅購入後の失敗談としてある典型的なケースです。なので、内覧時、不動産会社の担当者任せにするのは危険です。
大前提:不動産営業マンは「設備」のプロではないという事実
そもそも不動産会社の担当者は、物件の価格査定、法律関係、契約手続きといった「不動産取引」のプロフェッショナルです。しかし、給湯器やエアコン、換気システムといった「住宅設備」の専門家ではありません。彼らの設備に関する知識は、あくまで売主からのヒアリングや、過去の経験則に基づく一般的なものに過ぎません。
- 専門知識の欠如
担当者は、給湯器の銘板に書かれた型番から詳細な性能を読み取ったり、微かな異音から故障の前兆を察知したりすることはできません。彼らにとって給湯器は「お湯が出るか、出ないか」という二元論で判断されがちです。 - 「告知義務」の限界
不動産会社には、売主から知らされた物件の欠陥(雨漏りやシロアリ被害など)を買主に伝える「告知義務」があります。しかし、これはあくまで「知っている欠陥」に限られます。「12年経過した給湯器が、いつ壊れる可能性があるか」といった未来のリスクは、告知義務の対象外なのです。 - 「現状有姿(げんじょうゆうし)」のワナ
中古住宅の売買契約は、多くの場合「現状有姿」での引き渡しとなります。これは、「現状のありのままの状態で引き渡します」という意味です。つまり、引き渡し後に給湯器が故障しても、契約上は売主や不動産会社に責任を問うことは極めて難しいのです。
なので、不動産会社の「大丈夫ですよ」という言葉を鵜呑みにしてはいけません。 その言葉に悪意はないかもしれません。しかし、専門的な根拠もないのです。あなたの大切な資産と新生活を守るためには、担当者任せにせず、買主であるあなたが主体的に動く必要があります。
チェックリストを作るとしたら以下のようなものになります。
| チェック項目 | 確認するポイント | なぜ重要か? |
|---|---|---|
| ① 製造年月の確認 | 給湯器本体の銘板シールに記載された「製造年月」を確認。10年以上経過している場合は要注意。 | 寿命の客観的な指標。 10年超えはいつ故障してもおかしくない「レッドゾーン」と認識する。 |
| ② 号数(ごうすう)の確認 | 「RUF-A2405SAW」のように、型番に含まれる数字を確認。(この場合は24号) | 給湯能力を示す。家族の人数に対して号数が小さいと、冬場にシャワーの勢いが弱まるなど不便が生じる。家族構成に合った号数への変更も検討すべき。 |
| ③ 外観の劣化診断 | ・本体や配管接続部のサビ、白い粉 ・排気口周辺の黒いスス ・本体下部からの水漏れの痕跡 | サビや水漏れは内部劣化のサイン。ススは不完全燃焼の兆候であり、安全上のリスクも示唆する。 |
| ④ 稼働状況の確認 | (可能であれば)お湯を出してもらい、異音(「ポコポコ」「キーン」など)や異臭がないか確認。 | 内部の部品劣化や燃焼異常のサイン。故障の前兆である可能性が高い。 |
| ⑤ 設置環境の確認 | ・給湯器のタイプは何か?(壁掛け/据え置き) ・設置場所はどこか?(屋外/ベランダ/パイプシャフト内) | 交換時の機種選定や工事の難易度に関わる。特にマンションのパイプシャフト内設置の場合、交換できる機種が限定されるため事前確認が必須。 |
中古住宅では、キッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレといった水回り4点がすでに交換リフォーム済の物件もありますが、「給湯器は交換しておらず古いまま」のケースがありますので注意しましょう。
「10年」が目安の理由
とはいっても、一般の方が細かいところまでチェックするのは難しいため、最もシンプルなのは、目安の10年以上を経過しているのであれば、リフォームと合わせて交換するのが得策です。
給湯器を始め、日本の多くの設備は、精密な機械部品と電子基板の集合体なので、ほとんどが「10年」が目安になっています。
- 電子部品の寿命: 毎日過酷な環境で稼働する制御基板は、10年を境に故障率が急激に高まります。
- パッキン・配管の劣化: 内部のゴム製パッキンは硬化し、水漏れのリスクを常に抱えています。
- 燃焼効率の低下: 経年劣化により燃焼効率が落ち、知らず知らずのうちにガス代を無駄に消費している可能性があります。
また、温度差も耐久性に影響します。「冷たい水が給湯器に入ることによる温度差」は、給湯器の心臓部である「熱交換器」の寿命を縮める最大の要因の一つになっています。
実際、給湯器の交換を専門にしている人に話を聞くと、戸建住宅は地下からの水になるため温度差が大きく、給湯器の寿命を縮めやすいとのことです。
- 集合住宅:12年前後・・・屋上にある貯水塔から給湯器へ水が運ばれるため冬場でも温度差が小さい
- 戸建住宅:10年前後・・・地下から給湯器へ水が運ばれるため冬場は温度差が大きい
- 世帯数の多い戸建住宅(2世帯住宅など):8年前後・・・温度差が大きい+使う水の量も多い
もちろん中には、20年以上30年近く使い続けていたケースも存在はします。ですがそれは「非常に幸運な条件がいくつも重なった、極めて稀な例外」と考えた方がいいでしょう。
購入物件が「1年以上」空き家だった場合は要注意
また、購入する中古住宅が1年以上空き家だったのであれば、給湯器はたとえ10年未満でも、すでに寿命を迎えていると考えた方が安全です。
- 凍結による内部破裂のリスク
冬の間に内部に残った水が凍結し、心臓部である熱交換器や配管を破裂させているケースです。これは外から見ただけでは絶対に分かりません。いざ入居してお湯を出そうとした瞬間に、内部で大量の水漏れが発生する可能性があります。 - 部品の固着と腐食
長期間動かさないことで、お湯を循環させるポンプや、ガスを制御するバルブといった機械部品が固着(くっついて動かなくなること)してしまいます。また、内部に溜まったままの水が、配管の腐食を進行させます。 - 電子基板へのダメージ
誰も住んでいない家の湿気や結露は、電子基板にとって大敵です。気付かぬうちに基板がダメージを受け、正常に作動しなくなっている可能性があります。
「空き家期間が1年以上の物件」の給湯器は、走行距離が短くても誰にも乗られていない放置された中古車と同じです。見た目がきれいでも、内部は深刻なダメージを負っていると考えるのが賢明です。温暖と言われる姫路の南エリアでも1~2月の寒い時期に空き家だったりすると、凍結によるダメージも起こりえます。
給湯器をリフォームと同時に交換する3つのメリット
古い給湯器を壊れる前に交換することを、もったいないと感じるかもしれません。中古住宅を購入する際のリフォームと同時に給湯器を交換するメリットと、そのままで使用して壊れた後のリスクも考慮しながら、判断していきましょう。
- 工事費が圧縮され、コストを抑えられる
キッチンやユニットバス、洗面やトイレといった水回りのリフォームをおこなうのであれば、設備職人が何度も現場に出入りします。給湯器交換もその工程に組み込むことで、人件費や諸経費が最適化され、単独で依頼するよりもトータルコストを抑えることができます。 - 住宅ローンへ組み込めて、支払いの負担が軽くなる
これが最大のメリットです。数十万円の交換費用をリフォーム費用と合算して住宅ローンに組み込むことで、手元の現金を温存し、月々数千円程度の負担で最新の給湯器を導入できます。 - ランニングコストの削減
例えば、最新の省エネ給湯器「エコジョーズ」は、従来型に比べてガス使用量を約10~15%削減できます。毎月の光熱費が安くなることで、長期的に見て交換費用を回収していくことが可能です。 - 快適機能の追加
「自動お湯はり・足し湯」「追い焚き配管の自動洗浄機能」「浴室暖房乾燥機との連携」など、最新モデルは生活を豊かにする機能が満載です。日々のバスタイムが、格段に快適で便利になります。 - 故障リスクからの解放
「いつ壊れるか」という不安から解放され、心から安心して新生活をスタートできます。
結論:迷ったら交換。それが最も経済的で合理的な判断
中古住宅の購入において、あなたが設備診断の専門家になる必要はないです。
シンプルに、給湯器本体のシールを見て「製造年月日」を確認し、不動産会社に「この家の空き家期間」をヒアリングするだけです。
そして、その答えが、
- 製造から10年を超えている
- 1年以上、空き家だった
このどちらかに該当すれば、給湯器交換をリフォームの見積もりに含めた方がいいでしょう。
故障してから慌てて交換するよりも、リフォームと同時に計画的に交換する方法が、未来の安心と資産を守る、最もシンプルで確実な方法なのです。